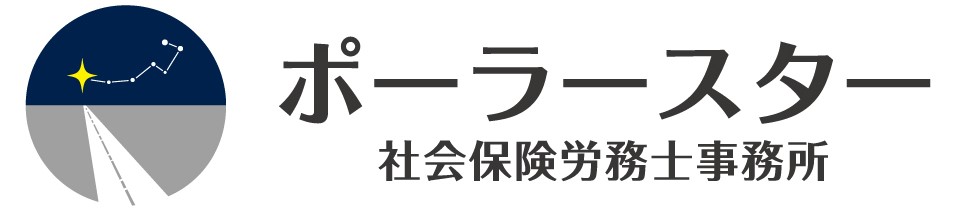静岡県警で勤務していた警部補Aの自殺は、長時間労働が原因であるとして、遺族(妻子と両親がそれぞれ提訴)が静岡県に対し安全配慮義務違反による損害賠償請求をおこなった裁判で、最高裁は県の安全配慮義務違反を認めました。
これにより、妻子訴訟と両親訴訟で異なる判断を示していたそれぞれの2審に対し、最高裁が統一の判断をしたこととなり、最高裁と同様の判断をした妻子訴訟については上告棄却、県の安全配慮義務違反を認めなかった両親訴訟については、2審(広島高裁)破棄・差戻となりました。
本件の争点は、主に①公務起因性の判断 と②安全配慮義務違反の有無 と考えます。
①公務起因性の判断については、最高裁は公務員の認定基準(「精神疾患等の公務災害の認定について」)の「発症直前の1か月以上の長期間にわたって、質的に過重な業務を行ったこと等により、1月当たりおおむね100時間以上の時間外勤務を行ったと認められる場合」を参照し、この要件に該当しないことをもって直ちに業務起因性が否定されるわけではないとしています。具体的には、本件では、複数の業務が重なった結果自殺直前の労働時間が急増し月100時間を超えていること、当直明けの非番の日における勤務を含め連続勤務が複数あったこと等を考慮して、「精神疾患の発症をもたらし得る過重な業務」に従事していたと判断しました(これ以外に発症に寄与した事情はうかがわれないとしています)。
②安全配慮義務違反の有無については、電通事件(平成12年3月24日・第二小法廷)を引用し、使用者は「業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当」としており、これは警察官(公務員)であっても変わりないとしています。そのうえで、勤務日誌や時間外勤務実績報告書等により警部補Aの具体的な業務の状況を把握できており、かつストレスチェックで最低評価だったことを考えれば、警部補Aの上司等が業務軽減措置をとらなかったことは注意義務違反にあたると結論付けました。
なお、補足意見にもあるとおり、地方公務員に適用される上述「精神疾患等の公務災害の認定について」や一般労働者に適用される「心理的負荷による精神障害の認定基準について」といった基準は、一定の合理性は認められるものの、法令ではないことから、あくまでも経験則上の一つの知見としてしん酌されることに留意が必要です。